1.ウオークマンで愛聴している楽曲。
☆ 女性ボーカリスト(国内) (2)
「ちあきなおみ」・・・アルバム「VIRTUAL CONSERT 2003 朝日のあたる家」
専門家でも有識者でもない自分には歌唱技術や歌唱力をはかる理論的背景はないが、とんでもなく歌の上手い人だなと思う。とにかく数曲聴いてみて欲しい。美空ひばりが嫉妬したという噂に真実味が増す。1曲聴くと「上手いなぁ」、数曲聴くと「上手すぎて呆れる」となる。
本当はYoutube等で動画を見た方が凄さがわかる。短いが濃いお芝居です。旦那に先立たれてから一切表舞台に出てこないのが惜しいが、その一途さがまた良いのだ。
このアルバムは選曲が秀逸で、1曲目の「百花繚乱」で恋心を軽快に歌い、「祭りの花を買いに行く」で友川かずきの佳品をさらっと流す。この曲に私はなぜか涙ぐんでしまう。
そして場末の飲み屋のママの独り言「紅とんぼ」で時代の雰囲気を見事に表現し、「朝日のあたる家」で女郎屋の歌で異様な雰囲気を醸し出す。「酒と泪と男と女」、河島英五のヒット曲。女性が歌ってここまで良いかと感心する。「ダンチョネ節」も入ってます。
1972年のレコード大賞曲「喝采」。私は12歳だったが、とんでもなく流行っていた記憶がある。
当時はまだ家族で見ていた「日本レコード大賞」で歌う彼女を見て、なんだかわからないが凄いなと感動した。歌詞の内容は実体験ではないが近いことはあったらしい。
終幕は「伝わりますか」。同名の素晴らしいアルバムでも終曲とされている、飛鳥涼(ASKA)が提供した歌。真っ向正面から歌いあげる姿が目に浮かぶ。
聴く者を歌詞の世界を引きずり込んでしまうほどに、その世界を体現できた唯一無二の歌姫。
「元ちとせ」・・・アルバム「ハイヌミカゼ」
巫女が歌ってる。初めて聴いたときそう感じた。 このファーストアルバムはメジャーデビュー曲「ワダツミの木」に尽きる。神気を纏っている。島唄をベースの発声方法のようで好みが分かれるかもしれない。だが、何曲か聴けば神性に気がつくはず。
ハイヌミカゼというのは奄美方言で南の風ということだそうだ。南風と書いてハエと読ませることがあるが根っ子は同じかも。南風海風(ハエウミカゼ)とか…。
表題の「ハイヌミカゼ」も良いが、日の当たる場所に初めてお披露目するなら「ワダツミの木」ということだろう。何かを渇望し、それが神により満たされる。ドラマチックな歌。
古い島唄を歌う動画を見たことがあるが、発声や節回しがとても特徴的で一般受けは難しいだろうなと感じた。神秘的ななにものかが憑依しているといった彼女のみの世界を見せられている印象であった。
奄美大島で奄美の人達と奄美の神の庇護のもと、いつまでも穏やかに楽しく暮らしていってほしい。そう願いたくなる歌い手で祈り手。
「ヒナタカコ」・・・アルバム「いずこの空」
祈りと抱擁と意志の人。
元ちとせとは少し異なるが、巫女に似た信仰を感じさせる歌手。車の運転中にラジオから流れてきた「いずこの空」の不意打ちで涙した。なぜかわからない。
帰宅後すぐにamazonでポチったのは10年前。届いたCDを手持ちのヘッドフォンの一番高価なやつで聴いたら、また涙が溢れた。なぜ涙溢れるのかしばらく考えてわかった。私の胸の内にある特攻隊への思いに共鳴しているのだ。特攻隊に思いをはせるとなぜか必ず涙ぐんでしまう。その悲しさ悔しさ腹立たしさ潔さ優しさに泣くのだ。彼女のことを詳しく調べたわけではないので「いずこの空」のモチーフを知らないが、そこに祈りと抱擁(救い)が確かにあると感じる。
数枚のアルバムを保有しているが、このアルバムの2曲目「春の花」は一番好きな歌。「つないだ手を引かれ、歩いた堤防に、芥子菜の絨毯、風に揺らいでいた…」と穏やかに始まる曲だが聴き終えれば、「人とは?」「この世とは?」「ここにいることの意味は?」といった実は答えの無い、逆に言えば無数の答えがある問いを、それはそれでよい、大いなる何かに任せるしかないと語っているような歌。
こういう曲、こういう歌手を知ることができたということ、それは大きな幸運と言える。もっともっと知られるべき歌手。NHKあたりが特番を制作してよい歌手かと思う。それによりたくさんの人の心が救われるはず。
4曲だけのミニアルバムだけれど、凡百のフルアルバムを凌ぐ価値があるので、全力でおすすめします。庶民の俗っぽさを許容し一緒に楽しむこともできる強き聖女。
「柴草玲」・・・アルバム「うつせみソナタ」
女の業を、制御された沈静と俯瞰で見つめる優しさ。
この歌手もラジオで知った。聞こえてきたのは「前山にて」。このアルバムでは終幕の歌。車の運転をしながら初めて聴いたとき、彼女が過ごした里山あたりの何気ない日常の記憶、何気ないが印象的なドラマを懐かしむ歌だと思ったが、何か普通じゃないなとも感じた。
気になったのでamazonでポチった。聴き終えて怖い人だなと感じた。女の業というか情念が心のかなり深いところで小さくしかし強く燃えている印象。若年時には抑え切れてなかったのではないか?
良く練られた歌詞、優しげな歌い方、本当は燃え盛りたい情念を抑制し慈しみの眼差しに変質させる術を身につけているようで、これまであまり出会ったことのない稀な才能。Cocco、沢田知可子への楽曲提供もされたようだが、よく知らない。女らしさというのはその根底に核となる男らしさがないと表現できないと思っているが、それが時々微かに見え隠れする。それが好ましい。
1曲目の「川辺」では叙情豊かに淡い恋の記憶、いや激しい片思い(かも)の淡いく切ない記憶を懐かしむ。そしてひとときの想い出は祭りの終わりとともに流れ去る。
2曲目の「祭りばやし」。たぶん町内レベルの祭。たぶん地域開発のあおりを受けて近い将来途絶えるであろう祭。だが今は皆で楽しむだけだ。あとはしらない。
アルバムタイトルのベースなのだろう7曲目の「虚蝉」。歌詞はなく数十秒で終わる。何を意図したものか。いわゆる空蝉のことだろう。本来は「現し身」「現せ身」で、この世にある人のことだが、いつしか「空せ身」つまり魂のぬけた人と変わり、そこからの連想で「空蝉」(蝉の抜け殻)となった。
「空」を「虚」に置き換えたのはおそらく彼女のたくらみ(笑)だろう。在ると思っていて油断していたら無くなっていた。無いと思っていたら突然現れて感情を揺さぶられる。記憶の不思議さ、想い出の楽しさと切なさ。
7曲を聴き終えて最後の「前山にて」を聴き始めた瞬間、「ああそうか」と思った。なぜだかはわからない。わからないが「そうなんだな」と腑に落ちた。そういうアルバム。
大人に憧れる思春期の子らに聴いてほしい。そして大人になってもう一度聴いて欲しい。そういう作品を生む女性。
※後書き
もう一人書く予定だったが力尽きた。文才の無い身としては、長い日数をかけて文章を考えてから筆をとり集中的に一気に書くスタイルで、これが大げさに言えば生命力を削られる。
言い訳はみっともないが、こういうことを吐露すると少しパワーが戻ってくるのでご容赦を。
次は男性ボーカリスト(国内)にする予定。人選は再考するが「柳ジョージ」は必ず入れます。そういえば「美輪明宏」は男性女性どちらに入れるべきか、悩むな…。
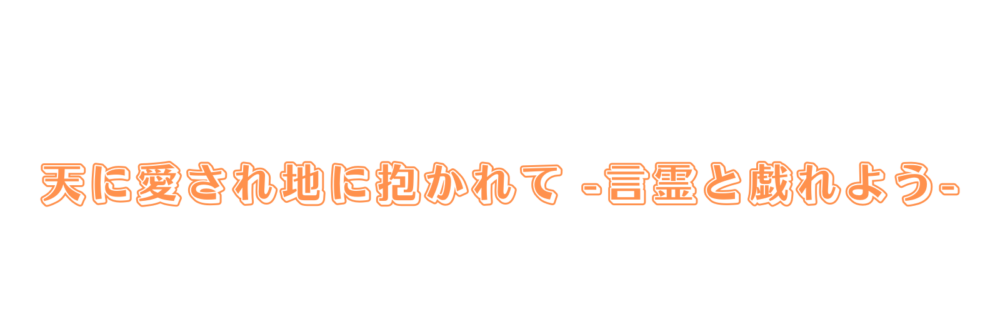


コメント